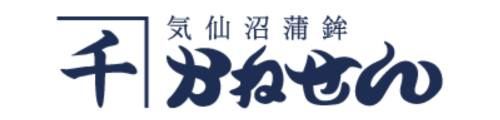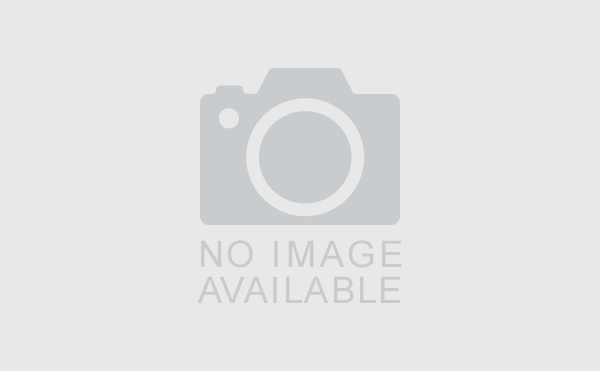気仙沼のもうひとつの名物 ─ サメ肉とかまぼこに受け継がれる港町の味~ふかひれだけじゃない、気仙沼の“すり身文化”を訪ねて~

港町・気仙沼とサメの深い関係
宮城県北部に位置する港町・気仙沼は、全国でも指折りの漁業都市として知られています。なかでも特筆すべきは、サメの水揚げ量が日本一であること。ヨシキリザメ、モウカザメ、アオザメといった多様な種類が水揚げされ、その豊富な資源は古くから地元の食文化を支えてきました。
「気仙沼のサメ」と聞くと、まず思い浮かぶのは高級食材のふかひれ。しかし、実はこの地の人々は、サメの身そのものも大切に活用してきたのです。鮮度の落ちやすいサメ肉を無駄にしないため、昔の人々は工夫を凝らし、すり身にして練り製品――かまぼこやはんぺん、ちくわ――として加工しました。
サメ肉は独特の性質を持ち、ほかの魚にはない魅力があります。繊維が細かく、気泡を抱き込みやすいため、ふんわりとした口当たりの良いすり身を作ることができるのです。これが、気仙沼の“ふわふわはんぺん”の原点でもあります。
港町で生まれた知恵と工夫が、日々の食卓を彩る味へと姿を変えた――。
気仙沼のかまぼこ文化は、そんな海の恵みと人の手仕事から育まれてきたのです。

サメ肉から生まれた気仙沼のかまぼこ文化
気仙沼では、古くからサメの身をすり身にしてかまぼこやはんぺん、ちくわなどの練り製品を作ってきました。その始まりは、港に大量に水揚げされるサメを“余すところなく使う”という漁師町の知恵から。サメ肉は独特の弾力と軽さを持ち、魚の中でも珍しく気泡を抱き込みやすい性質があります。この特性が、ふっくらとして口当たりの柔らかい“気仙沼流はんぺん”を生み出しました。
かまぼこ作りは、単なる食品加工ではなく、地域の季節行事や祝い事にも欠かせないものでした。正月や祭りの食卓には必ずといっていいほど並び、家庭ごとにお気に入りのかまぼこ屋がありました。昭和の中頃には、専業・兼業合わせて50軒以上のかまぼこ店が軒を連ね、港町の一角には魚の香りとすり身の湯気が立ちこめていたといいます。
当時のかまぼこ職人たちは、早朝から魚をさばき、石臼で丁寧にすり身を作るという手間のかかる仕事を日々続けていました。サメ肉は温度管理や混ぜ方によって仕上がりが大きく変わる繊細な素材。熟練の職人たちは、長年の経験と感覚で最適な加減を見極めながら、ひとつひとつを手づくりしていました。
こうして気仙沼では、サメという一見マイナーな素材が、地域の味として愛される練り物文化へと昇華していったのです。

消えゆく工房と、伝統を守るかねせん蒲鉾店
かつて50軒以上ものかまぼこ店が軒を連ねていた気仙沼。しかし、時代の流れとともに、原料の高騰や後継者不足、食文化の変化が重なり、現在ではわずか2社を残すのみとなりました。その中のひとつが、今もなお昔ながらの製法を守り続けるかねせん蒲鉾店です。
かねせん蒲鉾店は、創業当時から受け継がれる“石臼仕込み”にこだわり、職人の手作業による丁寧な製造を続けています。大量生産では決して再現できないふんわりとした食感と、口に入れた瞬間のやさしい旨み。それは、港町の空気とともに受け継がれてきた“気仙沼の味”そのものです。
また、伝統を守るだけでなく、新しい挑戦にも積極的です。隣町・南三陸町のライバルの蒲鉾店「及善商店」と共同で、常温で長持ちするかまぼこの研究開発に取り組み、旅のお土産にも最適な「旅するかまぼこ」を発売しました。競合関係を越えた地域連携によって、練り物文化の新たな可能性を切り拓いているのです。
一見、静かに見える小さな工房。その裏には、気仙沼の海とともに生きてきた人々の誇りと粘り強さがあります。ふかひれだけでは語れない“もうひとつのサメによって生まれた練り物文化”が、ここに今も息づいているのです。

未来へつなぐ“港の味” ─ 気仙沼の食文化を訪ねて
気仙沼のかまぼこ文化は、ただの地域特産ではなく、サメとともに生きてきた港町の歴史そのものです。サメ肉の特性を活かし、ふんわりとした食感のはんぺんやちくわを作り出してきた人々の知恵と技術。それは、海の恵みを余すことなく活かすという“もったいない精神”から生まれた、生活の工夫でした。
現在では、かまぼこ店の数こそ減りましたが、その味と技は確かに受け継がれています。かねせん蒲鉾店が守る伝統製法、そして及善商店との共同開発によって生まれた「旅するかまぼこ」など、新しい形で地域の食文化が息づいています。
気仙沼を訪れたら、ぜひ港町の工房をのぞいてみてください。ふかひれの陰に隠れがちな“もうひとつの気仙沼グルメ”──かまぼこ・練り物──を味わうことで、この町が歩んできた歴史の深さを感じられるはずです。
海とともに生き、魚とともに文化を育ててきた人々の物語は、今も静かに、しかし確かに続いています。